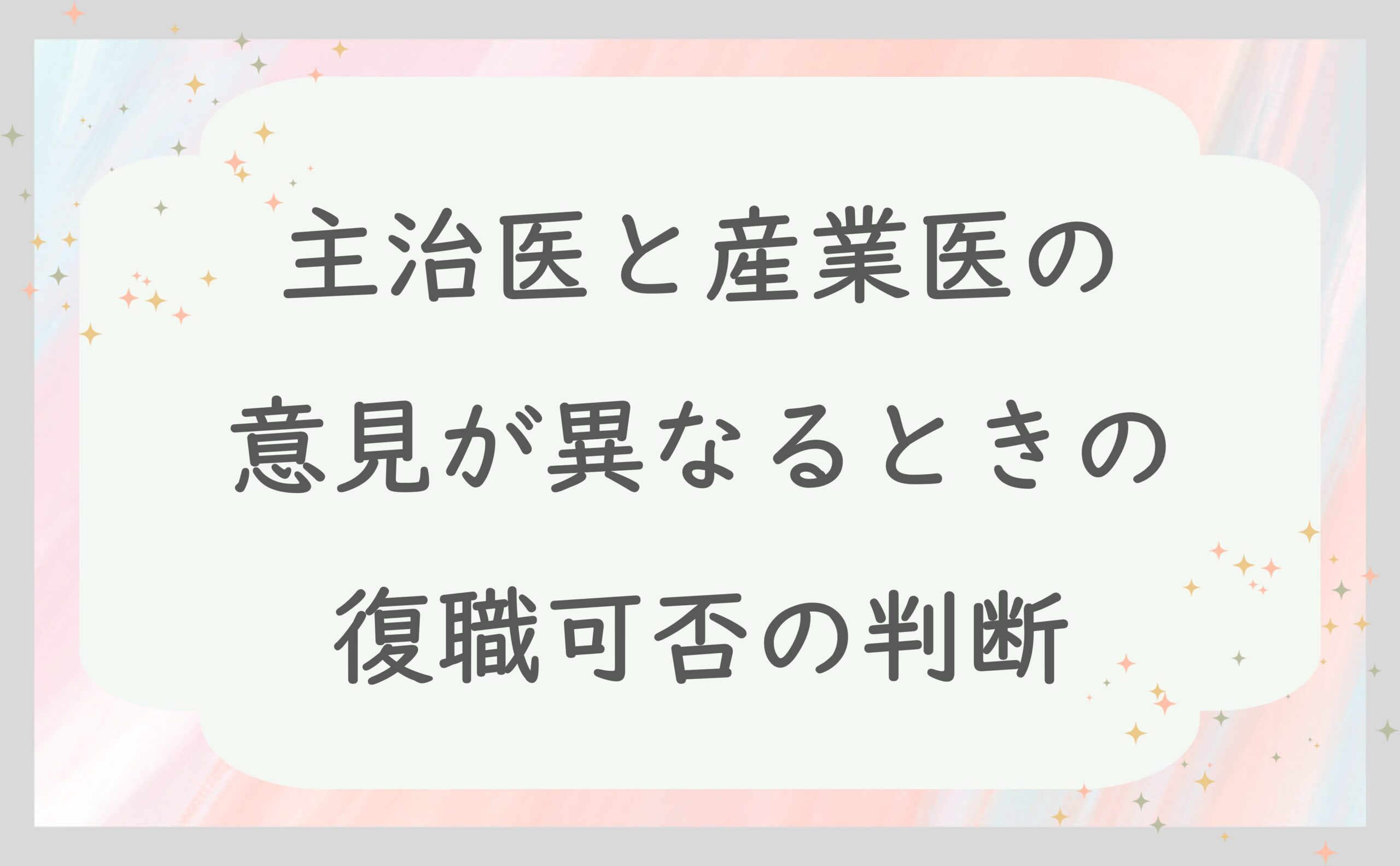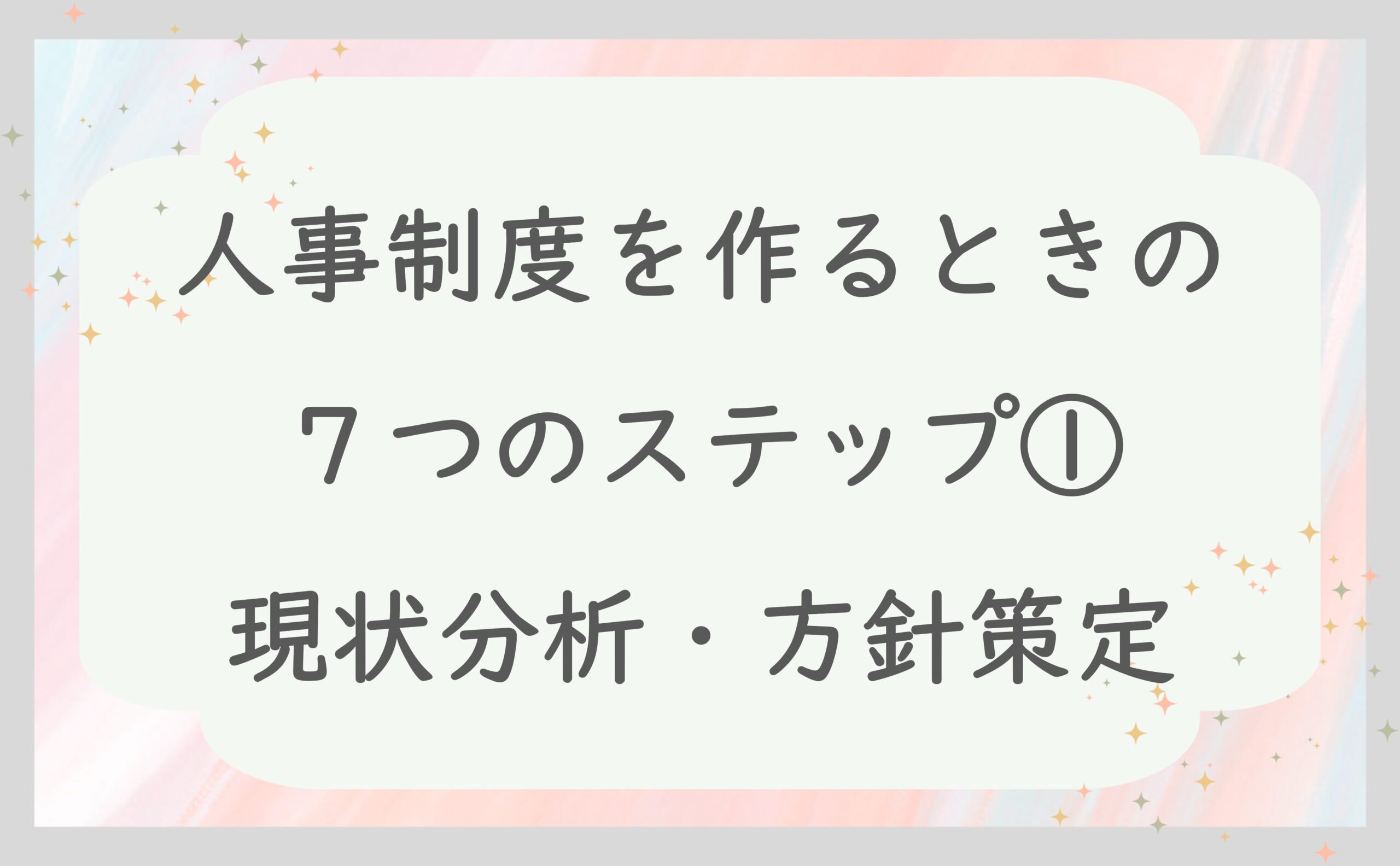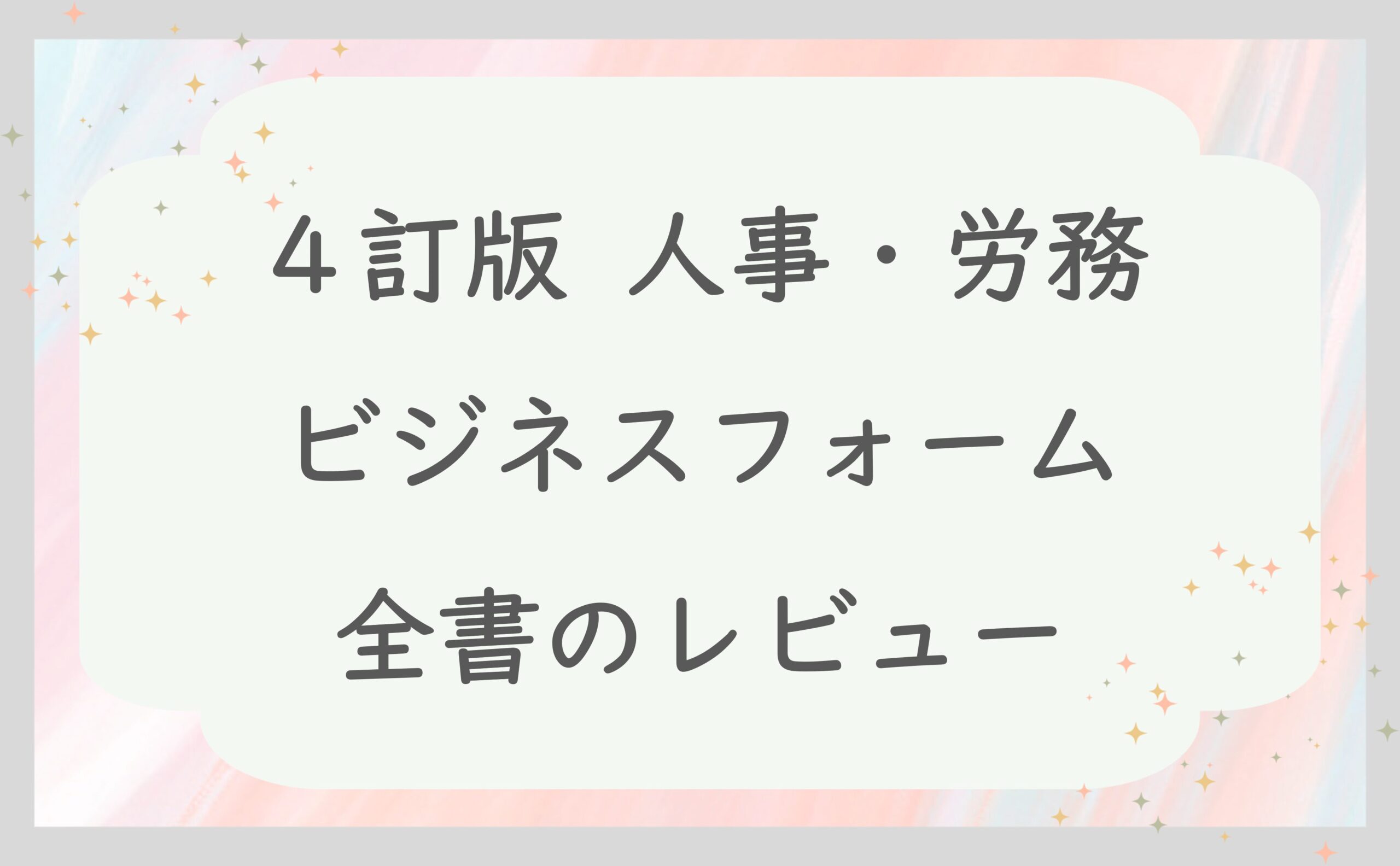社員がメンタルヘルス不調で休職していますが、「復職可」主治医診断書を添えて復職の申し出がありました。当社の産業医と本人が面談しましたところ、産業医から復職はまだ難しいとの意見を頂きました。
なお、主治医も産業医のどちらも心療内科や精神科の専門医ではありません。会社としては、主治医の意見も産業医の意見もどちらも尊重したいのですが、意見が真逆のため困惑しております。どうしたらよいでしょうか…?

私は、公衆衛生学(産業衛生)の分野で、「労働環境と健康への影響」をテーマに研究をし、博士(医学)資格を保有しています。今は、開業社会保険労務士として日々中小企業の経営者様への人事労務管理の助言指導をしています。
このコラムでは、メンタル疾患による休職からの復職可否について主治医と産業医の意見が異なる場合に会社が行う取り組みについて解説します。
リワーク支援を受けて頂くことをお勧めします
主治医の立場から
主治医の立場からは、「日常生活レベルでの健康状態の回復」をもって「復職可」の判断をしたのかもしれません。仮に、患者(労働者)が提供する勤務情報を把握していたとしても、会社が提供する勤務情報と内容に乖離がある場合には、主治医は正確な判断ができないかもしれません。
産業医の立場から
産業医の立場からは、「労働者」の健康管理の視点から、「働ける健康状態であるか否か」が判断のポイントになると考えます。よって、日常生活は問題なくできる健康状態まで回復していても、働ける健康状態までは、まだ回復していない場合は、「復職不可」と判断するでしょう。
日常生活レベルから働けるレベルまでの健康状態の回復
つまり、「日常生活レベルでの健康状態まで回復」と「働ける健康状態まで回復」までの間の健康状態であれば、主治医と産業医の意見が違うことは有り得ます。
復職するためには、「日常生活レベル」から「働けるレベル」まで休職者の健康状態が回復するのを待たなければならないと考えます。
具体的には、うつ病などのメンタルヘルス不調による休職から職場復帰を支援するリワークプログラムなどを利用することをお勧めしています。復職に際しては、リワークプログラムの受講を通じて「働ける健康状態まで回復」したかどうかを会社が判断し復職可否の決定をすることになるかと考えます。
リワークプログラムを通じて円滑な職場復帰がサポートされます
会社と主治医との面談
会社が求める「働ける健康状態」と主治医が「これくらいなら働ける健康状態だろう」の乖離を埋めるために、会社が主治医との面談を試みるという考えもあるでしょう…が、主治医から面談の意図を誤解されると、むしろ主治医との関係をこじらせることになりかねません。
労働者の同席または同意があれば、会社は主治医との面談は可能だと思いますが、すでに主治医は「復職可」の診立てを出しているわけです。「復職可」の判断を覆すことを目的とした面談(主治医と会社との面談)はお勧めいたしません。
一方で、復職基準に対する主治医と会社(産業医)との認識のギャップを埋めて、さらに「働ける健康状態へ回復するまでの対応について」会社と主治医で休職者の復職へ前向きな協議をすることには、大いに意味があると思います。
復職へ向けた取り組み
そこで、会社が復職可否の判断をする前に、休職者にはリワーク支援サービスを受けて頂き、職場復帰に向けた支援を受けて頂くことをお勧めします。
- Step 1主治医と産業医の意見が異なる
回復の定義にギャップがある状態
- 日常生活レベルでの健康状態まで回復
- 働ける健康状態まで回復
- Step 2主治医、労働者(休職者)、会社(産業医)復職に向けた協議
リワークプログラム受講について協議
(推奨)職場復帰支援プランを作成する - Step 3リワークプログラムの受講(休職者)
主治医、会社(産業医)も連携
- Step 4働ける健康状態までの回復を確認
主治医、産業医、リワーク支援の医師(可能であれば)の意見を聴く
- Step 5復職可否の判断
最終的には会社が復職可否を判断
(推奨)職場復帰支援プランを見直しする
リワーク支援サービスとは?
うつ病などの精神疾患で休職している方(労働者)が、円滑な職場復帰ができるように、復職に向けたプログラムなどの支援を行うサービスです。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の施設で、各都道府県に1~2か所あります。地域障害者職業センターには「リワーク支援」のサービスがあります。
地域障害者職業センターの「リワーク支援」サービスは、休職者本人、会社、主治医の3者による職場復帰に向けた共同作業をセンターがサポートするものですので、リワーク支援計画について、休職者本人、会社、主治医の同意が必要になります。
リワーク支援のプログラム受講料は雇用保険を財源としていますので「無料」です。そのため、民間企業の雇用保険適用事業所に雇用されている休職中の雇用保険被保険者が利用できます。国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人の職員は利用できません。
リワーク支援の期間は、3~4か月程度です。センターが休職者の住所から離れている場合、「通所に時間がかかり、むしろしんどい」というデメリットはあり得るかと思います。
リワーク支援のプログラム受講料は無料ですので休職者の経済的負担がないところがメリットですが、残念ながら、センターからのリワーク支援の結果を踏まえた復職可否の判断が頂けないことが、復職可否の判断でお困りの会社側にとってはデメリットになるかと思います。
民間医療機関のリワーク支援
民間の医療機関(心療内科・精神科)等によるリワーク支援です。健康保険制度や自立支援医療制度が使えますが、休職者には一部自己負担があります。
民間の医療機関のリワーク支援の場合、復職可否に関するご意見を頂けるかどうかは、各医療機関の対応によるかと思います。
民間のリワーク支援施設の探し方としては、信頼のおける組織からの情報提供をもとに探してはいかがでしょうか?例えば大阪府では、大阪府版事業場のメンタルヘルス こころの健康専門家ガイド(大阪産業保健総合支援センター)というサイトで情報提供されています。
障害福祉サービス
就労移行支援事業の一つで、「休職からの復職を目指す場合(復職支援型)」の支援です。
- 復職に必要な生活リズムの確立
- 体力や集中力の回復
- 主治医や産業医との連携 等
を通じ、円滑な職場復帰を目指すことを目的としています。
詳しくは「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発0329第7号 令和6年3月29日)」(厚生労働省)の「1(1)② イ 休職からの復職を目指す場合(復職支援型)」をご参照頂ければと思いますが、対象者、利用条件、利用期間を以下に引用します。
a 対象者
通常の事業所に雇用されている障害者であって、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものb 利用条件
以下の条件をいずれも満たした場合に利用できるものとする。
(a) 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない又は困難である場合
(b) 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
(c) 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合c 支給決定に当たっての留意事項
(略)d 利用期間
「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発0329第7号 令和6年3月29日)」(厚生労働省)
支給決定期間は、1か月から6か月までの範囲内で月を単位として定めること。
利用期間については、企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)とする。
- 地域障害者職業センターのリワーク支援
- 医療機関のリワーク支援
就労移行支援事業の復職支援型支援は、上記2種類のリワーク支援が使えない場合が前提になりますので、まずは、上記2種類のリワーク支援を検討すればよろしいかと思います。
まとめ
今回は、メンタル疾患で休職中の社員から「復職可」の主治医診断書を添えて復職の申し出がありましたが、産業医から復職はまだ難しいとの真逆の意見があったときの会社の対応について「即復職ではなくリワークを活用して円滑な職場復帰を進める」という案をご紹介しました。
主治医、産業医、リワーク支援の医師の3者の意見を聴くと、多数決でどちらかに決まるから、という理由ではありません。
「日常生活レベルでの健康状態まで回復」から「働ける健康状態まで回復」までの間の健康状態であれば、主治医と産業医の意見が違うことは有り得ます。
復職するためには、「日常生活レベル」から「働けるレベル」まで休職者の健康状態が回復していることを確認する必要がありますので、うつ病などのメンタルヘルス不調による休職から職場復帰を支援するリワーク支援の利用をお勧めしました。
復職に際しては、リワークプログラムの受講を通じて「働ける健康状態まで回復」したかどうかを会社が判断し復職可否の決定をすることになるかと考えます。
このコラムが、メンタルヘルス不調による休職からの復職可否について主治医と産業医の意見が異なる場合の対応にお困りの企業様へのお役に立てれば幸いです。