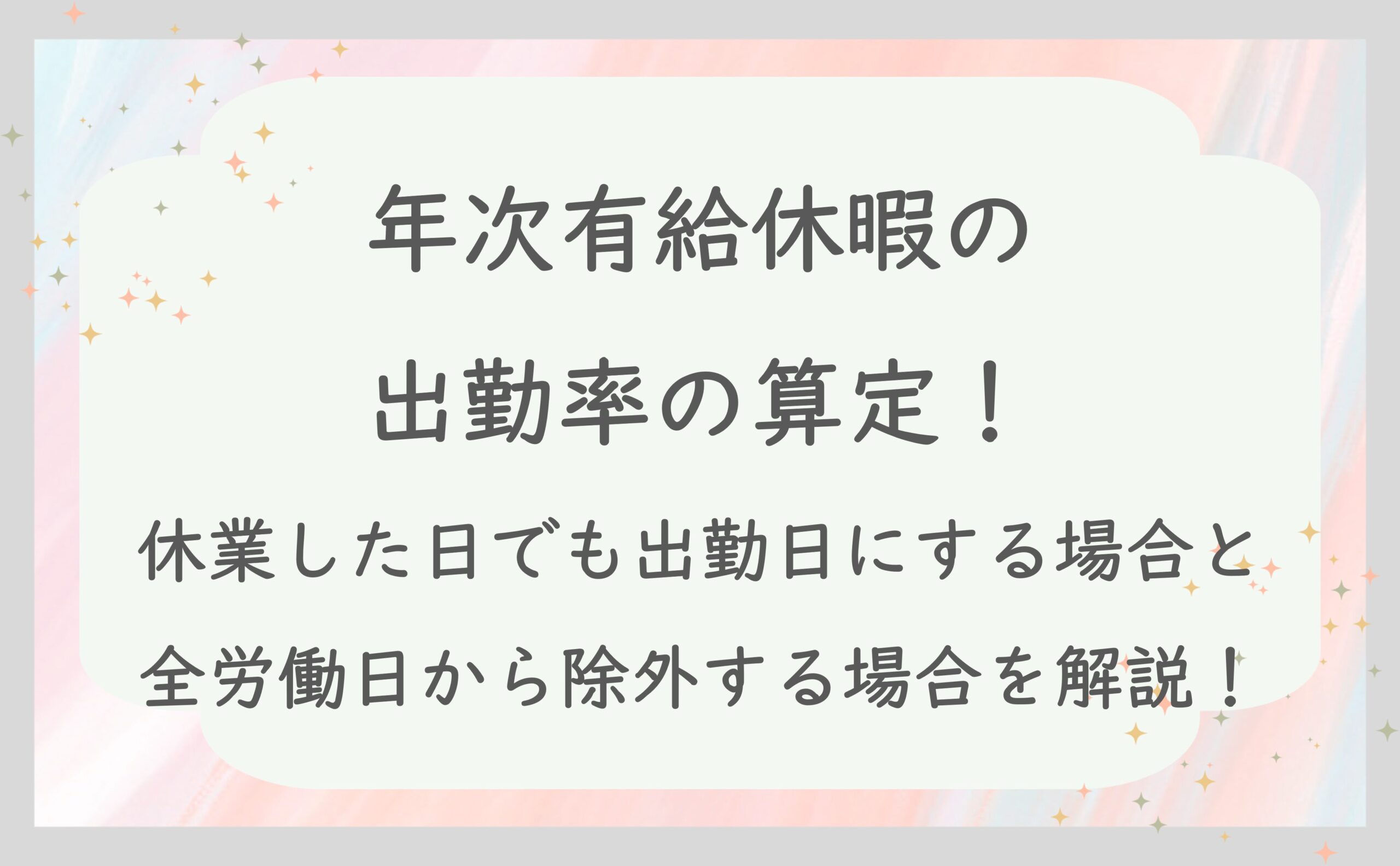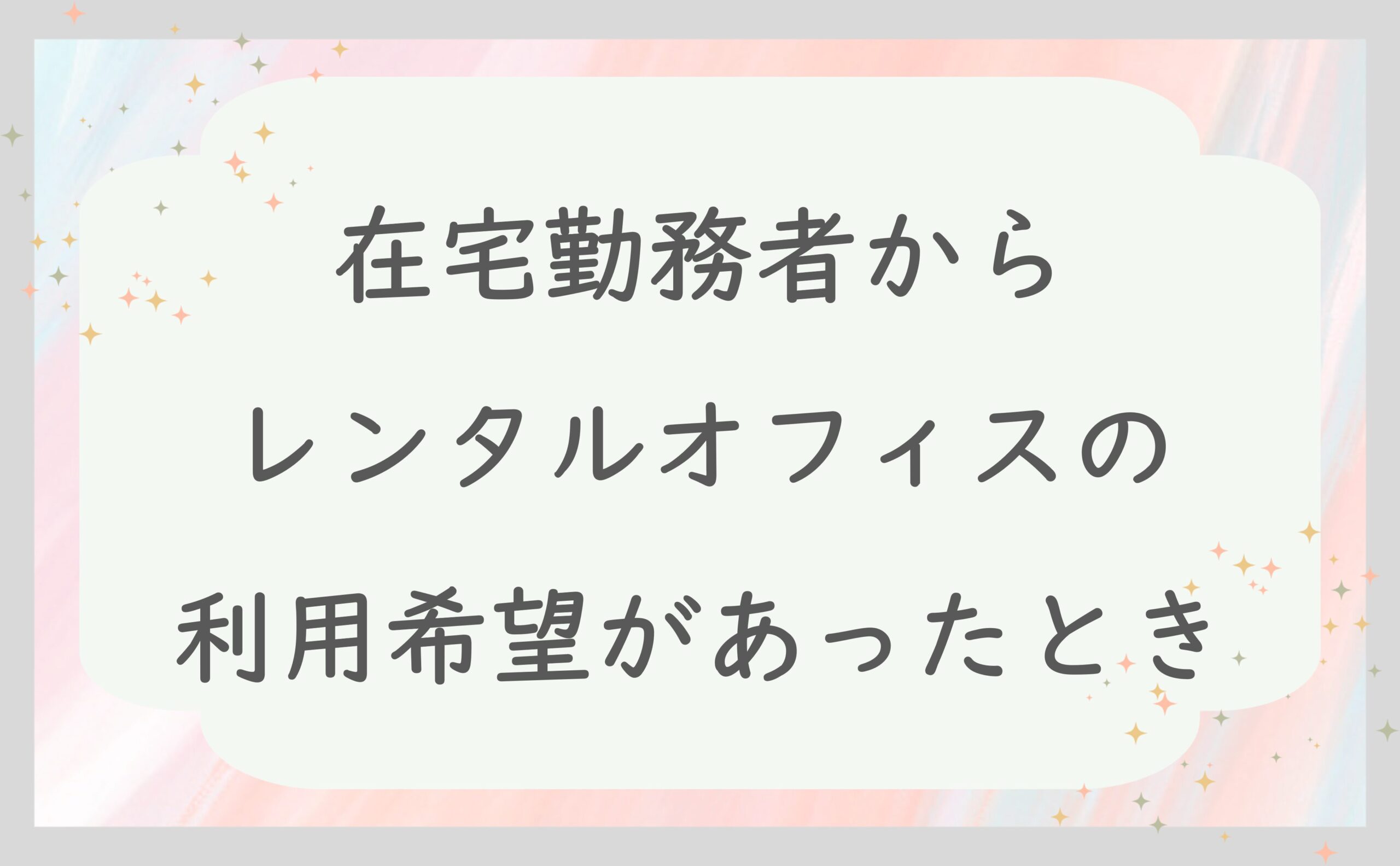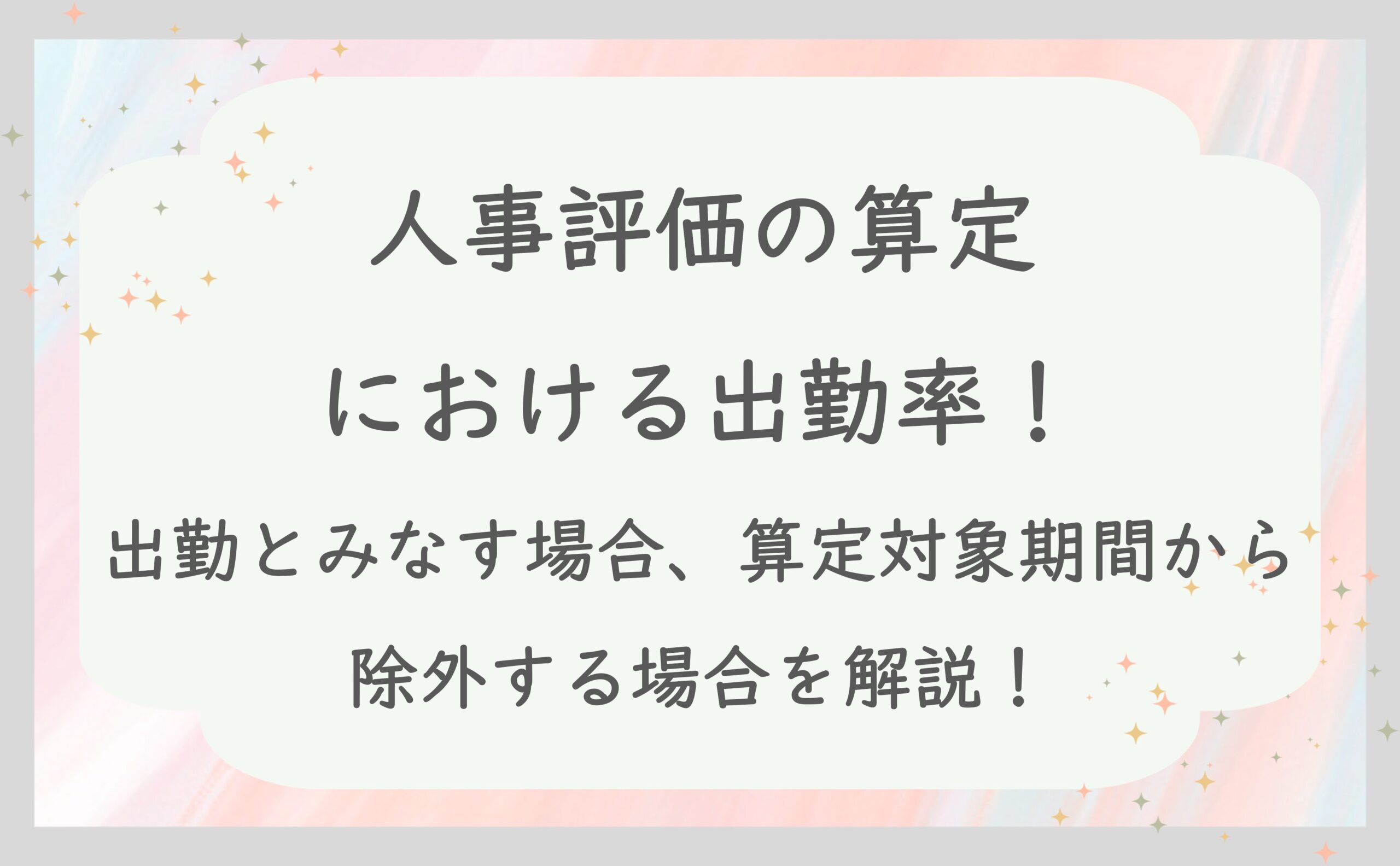労働基準法第39条に定められた年次有給休暇。発生するための要件は2つあります。
- 継続勤務要件(入社後6ヶ月間の継続勤務で付与され、以降1年ごとに付与される要件)
- 出勤率要件(入社後6ヶ月間の出勤率8割以上、以降1年間ごとの出勤率8割以上)
出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出所 労働基準法 e-Gov法令検索
②使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。(以下略)
一方で、最近の多様な働き方や職場のハラスメントによるメンタルヘルス不調などの増加傾向を背景に、人事労務の現場では次のような疑問が生じることがあるでしょう。
- シフト勤務などのため、労働日が特定されていない労働者の全労働日は何日でしょうか?
- 労災疑いのメンタルヘルス不調による休業も出勤日から除外してよろしいでしょうか?
- 子の看護休業、介護休暇、生理休暇は出勤日から除外できるのでしょうか?
この記事では、年次有給休暇の出勤率の算定について、
- 休業した日でも出勤日にする場合
- 全労働日から除外する場合
を中心に解説します!
全労働日とは?
全労働日とは、労働契約により労働義務のあるすべての日をいいます。
皆さまの会社でも就業規則や個別の労働条件通知書・雇用契約書に「所定労働日」や「所定休日」が定められているはずです。
全労働日数とは、シンプルに「所定労働日数」のことです。「総暦日数から所定休日数を差し引いた日数」も全労働日数です。

「所定労働日以外の日」は「所定休日」ということです!
全労働日に含めない日とは?
全労働日に含めない日は次の通りです。
- 所定休日
- 休日労働した日
- 使用者の責めにより帰すべき事由による休業の日
- 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
- 労使いずれの責めにも帰すべからず不可抗力による休業
- 代替休暇を取得し、終日出勤しなかった日
順番に解説します!
所定休日
所定休日とは、労働契約により労働義務の無い日です。
全労働日の定義に該当しませんので、当然に全労働日には含まれません。
休日労働した日
「休日労働した日」とは、所定休日に労働した日です。
実際に労働していますが、「労働契約により労働義務の無い日の労働」ですので、全労働日には含めません(出勤日にも含めません)。
使用者の責めにより帰すべき事由による休業の日
企業側の都合で労働者を休業させた日です。
終日休業の日は全労働日に含めません。(昭和63年3月14日基発150号)
正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
争議行為とは、憲法第28条に保障された団体行動権にもとづき、労働者の集団が使用者への要求を貫徹するために行う行為です。
争議行為の例としては、
- 同盟罷業(ストライキ)
- 怠業(サボタージュ)
- 作業所閉鎖(ロックアウト)
- ボイコット など
があります。
「正当な争議行為」については、労働組合法において刑事上および民事上の免責が与えられています。
よって、「正当な争議行為」により労務の提供が全くなされなかった日は全労働日に含めません。(昭和63年3月14日基発150号)
労使いずれの責めにも帰すべからず不可抗力による休業の日
「労使いずれの責めにも帰すべからず不可抗力による休業」とは、たとえば、天災事変などのために事業場の施設・設備が直接的な被害を受けた場合の休業のことです。
年次有給休暇における出勤率算定において、全労働日に含めません。(昭和63年3月14日基発150号)
代替休暇を取得し、終日出勤しなかった日
代替休暇とは、労働基準法第37条第3項に基づく、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の休息の機会を確保することを目的とした有給休暇です。
行政通達(平成21年5月29日基発0529001号)より、労働者が代替休暇を取得し、終日出勤しなかった日は全労働日から除きます。
5 代替休暇と年次有給休暇との関係
代替休暇は、法第37条第3項において「(第39条の規定による有給休暇を除く。)」と確認的に規定されており、年次有給休暇とは異なるものであること。
なお、法第39条第1項は、六箇月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における全労働日の八割出勤を要件としているが、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこと。
出所 平成21年5月29日基発0529001号
出勤日とは?
所定労働日に出勤した日です。
欠勤や私傷病休職など、労働者の責めに帰すべき休業の日は当然に出勤日に含めません。
ただし、遅刻や早退など、その日の所定労働時間の一部でも労働した日は出勤日に含めます。
出勤したものとみなす日とは?
ただし、出勤していない日でも「出勤したものとみなす日」も出勤日に含める必要があります。
年次有給休暇における出勤率の算定で「出勤したものとみなす日」は次の通りです。
- 業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間
- 育児休業(育児・介護休業法 第2条第1号に定める育児休業)
- 介護休業(育児・介護休業法 第2条第2号に定める介護休業)
- 産前産後休業(労働基準法 第65条)
- 年次有給休暇として休んだ期間
- 労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日(平成25年7月10日基発0710第3号)
労災による休業、育児・介護休業、産前産後休業
労働基準法 第39条第10項に次のように定められています。
⑩労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
出所 労働基準法 e-Gov法令検索
年次有給休暇として休んだ期間
労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日
八千代交通事件の判決(最一小判平成25年6月6日)を受け、労働基準法第39条の解釈が行政通達(平成25年7月10日基発0710第3号)にて更新されました。
第1(略)
2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一) 不可抗力による休業日
(二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(三) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(以下略)
出所 平成25年7月10日基発0710第3号
出勤率に含める必要がない日は?
法定の休暇
年次有給休暇における出勤率の算定で、先に述べた以外の法定休暇のすべてを出勤したものとみなす必要はありません。
- 生理休暇(労働基準法 第68条)
- 子の看護休暇(育児・介護休業法 第16条の2)
- 介護休暇(育児・介護休業法 第16条の5)
- 育児目的休暇(育児・介護休業法 第24条)
- 裁判員休暇(労働基準法 第7条)
- 公民権行使のための休暇(労働基準法 第7条)
- 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置による休業(男女雇用機会均等法 第12~13条)
法定外の休暇・休業
就業規則等に定める法定外の休暇・休業も、年次有給休暇の出勤率の算定上、出勤日に含める必要はありません。
- 慶弔休暇
- 病気休暇
- リフレッシュ休暇
- 教育訓練休暇 など
代休を取得した日は?

休日出勤した日は全労働日に含めないことはわかりました。
それでは、代休を取得した日は、
- 全労働日から除くのか?
- 出勤日に含めるのか?

残念ながら、法令や行政通達には示されていません。
「代替休暇と年次有給休暇の関係」の行政通達の考え方が近いと考えます。
5 代替休暇と年次有給休暇との関係
代替休暇は、法第37条第3項において「(第39条の規定による有給休暇を除く。)」と確認的に規定されており、年次有給休暇とは異なるものであること。
なお、法第39条第1項は、六箇月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における全労働日の八割出勤を要件としているが、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこと。
出所 平成21年5月29日基発0529001号

一方で、代休制度は就業規則により、取得の義務付けの程度が会社により異なりますので、その点についても考えてみましょう。
- 年次有給休暇よりも代休を優先して取得させる
- 代休の取得に義務付けはない など
もし、代休取得が個々の労働者の意思により決定される場合は、代替休暇制度と同様の扱いでよろしいでしょう。(代休取得日は全労働日から除く)
一方で、代休取得が個々の労働者の意思よりも会社からの業務命令により決定される場合は、「労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日」と解釈できる可能性があると考えます。(代休取得日は出勤日とみなす)

その代休取得がどれだけの労働者へ強制されているのかが、判断材料になるかもしれません。
就業規則の定めや、労使慣行といった実態を確認しましょう。
より安全側に考えるのであれば、代休取得日は出勤日とみなします。
「出勤日に含む」ほうが「全労働日から除く」よりも、労働者に有利な条件になります。
例えば、1年間の所定労働日数が240日の場合、年次有給休暇の発生要件である出勤率8割以上となる出勤日数は192日以上になります。次の条件で比較してみましょう。
- 出勤日数 191日
- 欠勤日数 48日
- 代休日数 1日
代休を出勤日に含むと、
出勤率 =(191日+1日)÷ 240日 = 0.8 ≧ 0.8
→ 出勤率8割以上の要件を満たします
代休を全労働日から除くと、
出勤率 = 191日 ÷ (240日-1日)≒ 0.799 < 0.8(小数点以下切り捨て)
→ 出勤率8割未満のため要件を満たしません
よって、「出勤日に含む」ほうが「全労働日から除く」よりも、労働者に有利な条件になります。
まとめ
年次有給休暇の出勤率は次の式で求めます。
出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日
出勤日に含む日
- 所定労働日に出勤した日(遅刻や早退など一部でも出勤した日を含む)
- 労災による休業期間
- 育児休業の期間
- 介護休業の期間
- 年次有給休暇として休んだ期間
- 労働者の責に帰すべき事由によるとは言えない不就労日(平成25年7月10日基発0710第3号)
全労働日(=所定労働日)から除く日
- 所定休日(所定休日に労働した日を含む)
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業
- 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
- 不可抗力による休業
- 代替休暇として休んだ日
このほか、
- シフト勤務などのため、労働日が特定されていない労働者の全労働日の日数を特定する必要があること
- 労災疑いのメンタルヘルス不調による休業は、労災認定の審査を待ってからでも遅くないこと
- 子の看護休業、介護休暇、生理休暇など、出勤日から除外できる法定休暇の例
を紹介しました。
年次有給休暇の出勤率算定に関する法令を正しく理解することにより、過不足なく適切に年次有給休暇を付与して頂ければと思います。