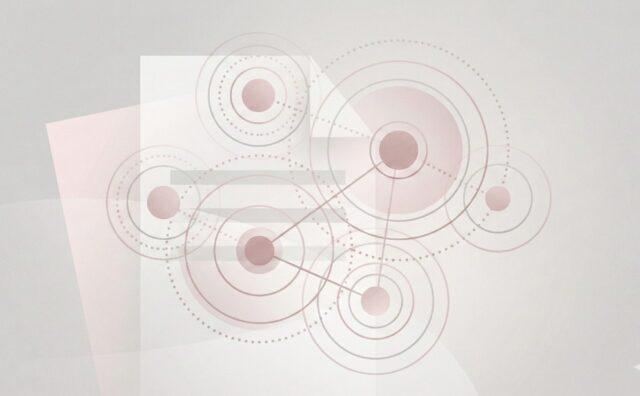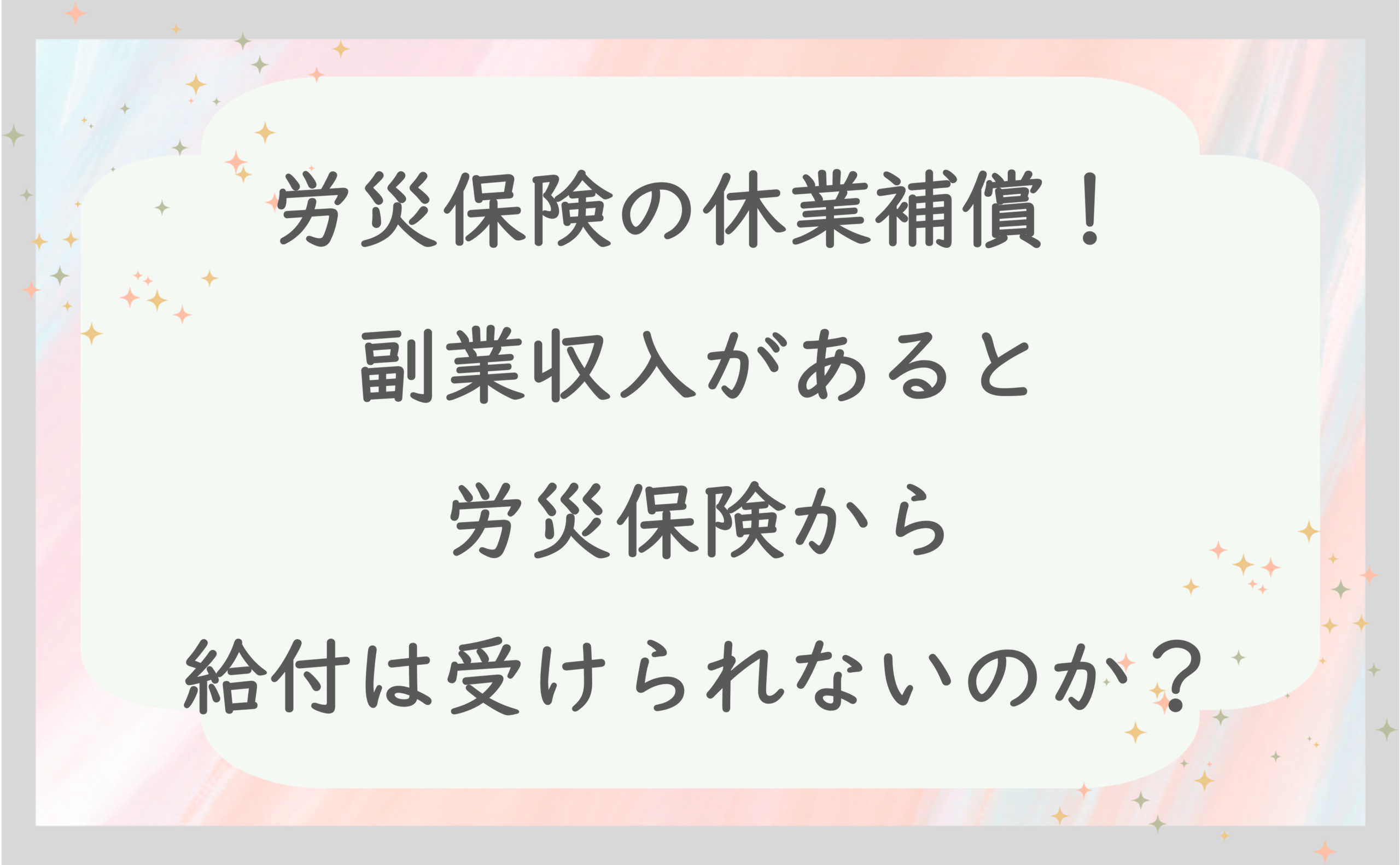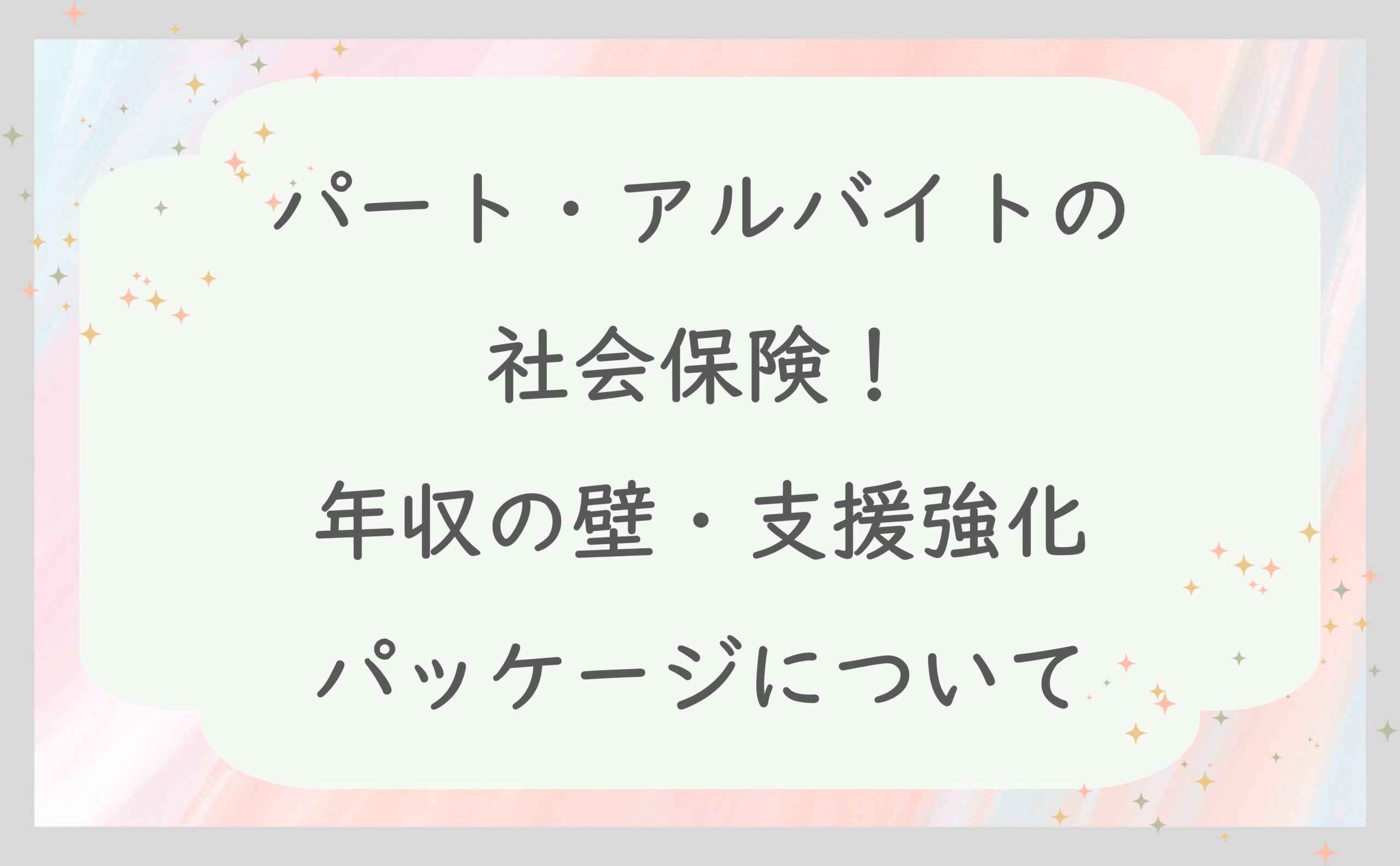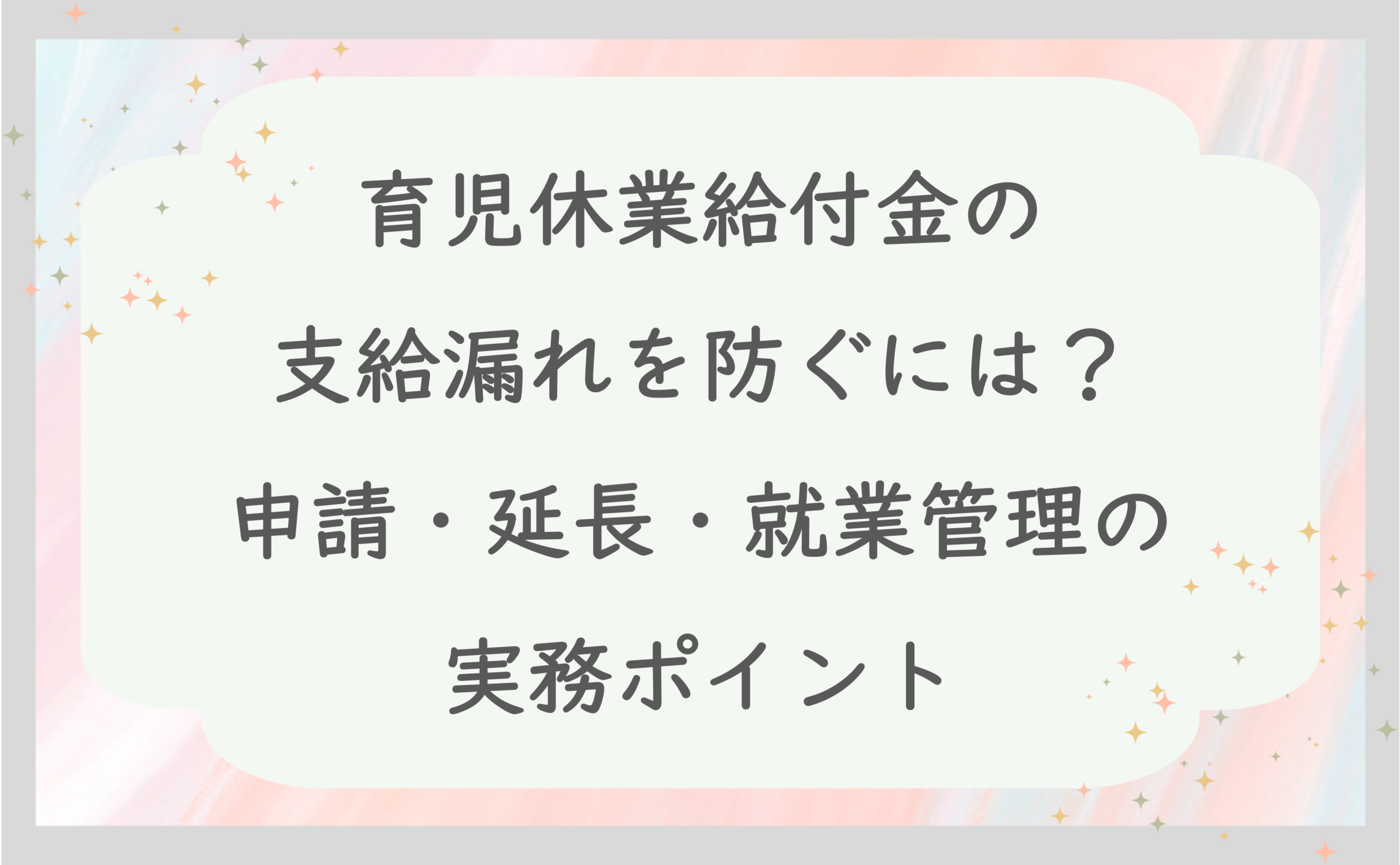社員が職場で怪我をして労災で休業中です。その社員は副業として自分が所有している不動産を貸していて家賃収入があります。休業中も家賃収入があるのですが、労災保険からの給付に影響がありますか?

社員が労災で休業中に副業で不動産賃貸から家賃収入があっても、これは賃金とはみなされません。労災保険の休業補償給付は、あくまで本業からの賃金喪失を補填するものであり、資産収入は給付に影響しません。したがって、家賃収入が給付額や受給資格に直接影響を及ぼすことはありません。
一方で、様々な形態で副業をしている社員さんもいますので、今後のために整理して考えてみましょう。
この記事では、労災休業補償の給付を受けるための要件(業務災害・療養中・賃金未受領)、給付額の仕組み、複数就業や副業がある場合の対応、実務上の注意点や申請時の書類準備などのポイントをできるだけわかりやすく説明します。
また、「収入の有無ではなく就労の有無で給付の可否が判断される」ことや、軽易作業の扱い、休業期間のカウント方法などについても解説します。
先に結論|「収入の有無」ではなく「就労の有無」で判断される
労災の休業(補償)等給付は、「収入があるかどうか」ではなく、「就労(実際に働いたか)と当該事業場から賃金を受けたか」で判断されます。
制度上の支給要件は
- 療養のために
- 労働することができず
- (その事業場から)賃金を受けていない日
の第4日目以降に、給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=実質80%が支給される、というシンプルな枠組みです。
ここでいう「賃金」とは雇用の対価を指し、自営業での売上や利益は賃金ではありません。そのため、自営の“収入が入っている”だけでは、本業側の「賃金を受けていない」要件を直ちに崩しません。重要なのは、療養中に実際の作業=労務を行ったかどうかです。
一方で、実作業を継続している場合は要注意です。たとえば療養中にパソコンで仕事ができる場合など業務遂行性のある行為を継続していれば、「労働することができない」の要件充足が疑われ、不支給または部分算定(一部就労日扱い)となる可能性があります。逆に、不動産を貸しているなど受動的に発生する収益にとどまるなら、原則として本業側の休業判定に直接の影響は及ばないでしょう。
複数就業(雇用×雇用)の場合は整理が少し異なります。給付基礎日額は全就業先の賃金を合算して決めますが、「賃金を受けていない日」の判定は事業場ごとに行います。つまり、A社は無給(休業)、B社は有給(または就労)という日の扱いは、A社については休業する日としてカウントされ得ます。ここでも“自営の収入”は賃金ではないため、合算や判定の対象外です。
実務では次の点を押さえておくと安心です。
- 医師の就労可否(在宅軽易作業の可否を含む)と実際の作業内容・頻度が矛盾しないようにする。
- 一部就労・手当支給があった日は、就労や支給額を控除して部分算定されるため、日ごとの実態を記録しておく。
- 申請時は本業の賃金支給状況の証明を適切に添付。自営のみの場合は「賃金証明」という概念自体がないため、自営の作業有無を説明できるメモ(作業日誌・ログ)を残しておくと審査がスムーズです。
まとめると、カギは“お金が入ったか”ではなく“働いたかどうか”。本業の出勤ができず賃金も出ていないなら、その日は休業する日に該当します。自営がある場合は、受動的収益は基本OK/実作業は要注意―この線引きを意識して、医師意見・作業実態・賃金の3点を整えておくことが、不支給リスクを下げる最善策でしょう。
労災の休業(補償)等給付の基本
休業(補償)等給付は、①業務災害の療養中で、②そのために労働することができず、③当該事業場から賃金を受けていない日の第4日目以降に支給されます。
金額は給付基礎日額の60%(休業〔補償〕給付)に20%(休業特別支給金)が上乗せされ、実質80%が日ごとに支給されるのが原則です。
所定労働時間の一部だけ働いた日や、一部手当の支払いがある日は「部分算定」となり、実際に支払われた賃金分を控除して計算することが原則ですが、「労働可能性の認定」はあくまで労基署長の裁量により医師意見や就労実態により総合判断されます。
なお、労災の保険給付は所得税非課税である一方、別途行っている自営の事業所得は通常どおり課税対象です。
副業のタイプ別に整理する(雇用か、自営か)
「副業」が雇用か自営かで、論点が変わります。
雇用による副業(=複数就業者)の場合、2020年改正により非災害発生事業場の賃金も合算して給付基礎日額を決定しますが、「賃金を受けていない日」の判定は事業場ごとに行います。
ただし、「労働することができない」の判定については、”本業では休業し、副業は軽作業なので働ける”という場合は給付の対象にならないのでご留意ください。
「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。
複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
令和3年3月18日/基管発0318第1号/基補発0318第6号/基保発0318第1号/
一方、自営(不動産所得・事業所得など)の収入は賃金ではないため、給付額の算定合算の対象外です。ただし、自営で実作業(就労)をしていれば「労働できない」要件の充足が問題になり得るため、収入の有無ではなく、就労実態の有無で線引きするのが実務のコツです。
ケースで理解する|本業が出勤不可のとき
同じ「本業が出勤できない」でも、副業の態様で結論が分かれます。
①自動収益のみなら、原則として本業側の「賃金不支給・就労不能」判定に影響しにくいです。
②在宅副業で軽易作業を実施している場合は、医師の就業制限と矛盾しない範囲か、作業の頻度・内容・時間を説明できるかが審査の焦点になるでしょう。
③雇用の副業で実際に就労していれば、一般に「労働可能」と評価され、本業側の休業給付は不支給または部分算定の扱いになり得ます。
特別加入(自営)の場合のポイント
もし自営側で特別加入している場合、自営での災害に対して別枠で保護されます。
給付基礎日額は3,500〜25,000円(16段階)から選択し、これが休業・障害・遺族等の各給付の土台になります。
要件は、当該業務の業務遂行性がある作業について全部労働不能であること。
療養中に現実の作業(現場確認、打合せ、制作・運転等)ができてしまうと、休業給付の対象外と判断され得ます。
なお、本業(雇用)での被災に関する給付は、特別加入の有無に影響されません(合算は雇用賃金のみが対象)。
申請・審査で詰まりやすい実務ポイント
まず、賃金支給状況の証明を正確に。所定休日・欠勤・有給の扱い、各種手当の支給有無を日ごとに整えます。一部就労や半日勤務がある日は、勤務実績と支給額がわかる資料(勤怠・賃金台帳)を添付し、部分算定の根拠を明確にします。複数の雇用がある場合は、非災害発生事業場の賃金情報も提出が必要です。自営のみの場合は賃金証明という枠組みがないため、医師の就労可否と矛盾しない範囲で、作業日誌・操作ログ・依頼メールなどの就労実態の有無を示すメモを残しておくと、照会対応がスムーズです。
ポイントは就労の有無
「副業収入があれば不支給」は誤りで、ポイントは就労の有無です。また、健康保険の傷病手当金の“〇%基準”を労災に持ち込むのも誤り。労災の休業(補償)等給付は日額80%(60%+20%)が原則で、一部就労等は部分算定で処理します。さらに「他社で有給なら全体が×」という誤解も散見されますが、賃金不支給の判定は事業場ごとです。自営の収益は賃金ではないため、合算の対象から外れます。
企業・労働者それぞれのチェックリスト
会社(人事・労務)側
- 勤怠・賃金台帳・各種手当の支給基準を日単位で整備
- 休業日・一部就労日・有給取得日の区分けを明確に
- 兼業・副業届の運用(申告制)と情報共有フローを用意
- 医師の就労可否(軽易業務の可否含む)を職務と照合
労働者(申請者)側
- 医師意見(就業制限)・通院予定の原本控えを保管
- 就労実態の日誌化(作業内容・時間・頻度)
- 雇用の副業がある場合は、他社賃金情報の提出準備
- 自営の場合、実作業の有無を示す客観ログを残す
税務・会計
- 労災給付は非課税/自営所得は課税の線引き
- 経費・売上計上の証憑整理(後日の説明がしやすい形で)
まとめ|不支給リスクを下げる運用と相談先
不支給リスクを下げる最短ルートは、「医師意見」×「就労実態」×「賃金の有無」の3点整合を崩さないことです。就労していない日は賃金不支給を明確に、就労した日は部分算定の根拠資料を揃える。そして、雇用か自営かで賃金の概念が異なる点を関係者で共有しておくと、照会対応が格段に楽になります。運用で迷うときは、所轄労基署への事前相談や、社労士による申請書の事前レビューを活用してください。最終判断は事実認定に基づくため、日ごとの記録こそが最大の防御になるでしょう。